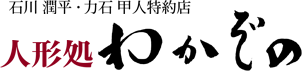鎧兜の技 ~ 力石 甲人 鎧兜の技術
「わかぞの」がお薦めする(ご紹介する)大鎧とは
平安期~鎌倉、室町時代に渡って大将の晴れ着として素晴らしい甲冑がつくられました。
戦いを目的としての着用鎧とは違い、神社に祈願奉納を目的とした奉納鎧と呼ばれ 国宝甲冑として世界に類がない程、その造形美は世界的にも絶賛されています。
「わかぞの」では、国宝甲冑(大鎧)を参考にした 「力石 鎧秀」「力石 甲人」による奉納鎧をご紹介、お薦めしております。
まさに、お子様の健やかなご成長を祈り願う御節句飾りとして最も相応しい鎧飾りと云えるのではないでしょうか。
デッサンによる造形美の追及
甲人の鎧・兜は芸術作品の基本でもあります。
三角(円錐)/丸(球)/四角(円柱)に収まるようにデッサンし、飾り鎧・兜としての理想の形を求めてから制作を始めています。
あらゆる芸術作品は三角(円錐)/丸(球)/四角(円柱)に収まる形が最も安定感を与え、理想とされています。
見る者に安定感を与えその造形美に感動する職人技
どちらから鑑賞しても美しくつくられています
鎧兜の造形美に感動する職人技
 弦走韋 |
|
弦走韋
正面から左脇(わき)に画韋を張り弦走(つるばしり)とよぶのは、弓射のときに弓弦が引っかからずに弓弦の走りをよくする配慮からです。
鹿韋は、繊維が細かく強靭なため古来から武具などに多く用いられていました。
この不動明王は、魔除けの意味から意匠として好まれた紋様です。
|
|
 大袖 |
|
|
|
 蝙蝠付 |
|
蝙蝠付
腰のあたりの部分です。
そのすきまには壺板(つぼいた)に草摺1間を蝙蝠付(こうもりづけ)を用いて取り付けた脇楯(わいだて)を当てます。前後は鞍で重量を支えられますが、この左右は垂れ下がるのでその重量を補強するための装備です。
|
|
 後ろ姿 逆板 |
|
後ろ姿 逆板
逆板は着脱と屈伸の便と袖の調節等、考慮して三の板との威付けを逆にしたもので、中央に大座(だいざ)の鐶(かん)を打ち総角(あげまき)を結び、袖の懸緒(かけお)と水呑(みずのみ)の緒(お)を控えますが心臓部をもニ重の防御そして後ろ姿も綺麗にみせる施しとなっており、国宝鎧には必ず装備されております。
|